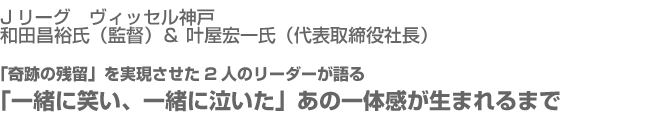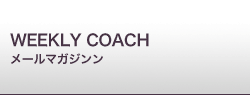2010年J1リーグ。シーズン序盤から負傷者が続出し、中盤以降もベストメンバーが組めない中、最終節まで9節連続で降格圏内にとどまっていたヴィッセル神戸。しかし、2人のリーダーを中心とした愚直かつ継続的な取り組みにより、クラブには徐々に結束力が生まれ、最後の最後に逆転J1残留を果たしました。そんなヴィッセル神戸の一体感を生み出した要因は何だったのか。今回は、神戸に足を運び、和田昌裕監督と叶屋宏一社長にお話を伺いました。

- 和田 昌裕氏
-
(ヴィッセル神戸監督)
順天堂大学卒業後、松下電器産業サッカー部(現ガンバ大阪)入部。1995年からヴィッセル神戸に在籍。引退後は、ヴィッセル神戸ホームタウン事業部普及指導コーチ、サテライトコーチ、ジュニアユース監督、ヘッドコーチ、強化部長チーム統括本部長などを経て、2010年9月より監督に就任。2011年シーズンも引き続き指揮を執ることが決まっている。

- 叶屋 宏一氏
(株式会社クリムゾンフットボールクラブ 代表取締役社長)
上智大学経済学部卒業後、三和銀行株式会社入行。その後、メリルリンチ証券会社東京支店、バンクオブアメリカ証券会社東京支店 営業本部長を経て、2004年、株式会社クリムゾンフットボールクラブ(ヴィッセル神戸の運営会社)入社。専務取締役就任。2010年から代表取締役社長に。
揺るがない信念が、チームを一つに
----降格間違いなし、という状況からの逆転残留劇、見事でした。まずは残留が決まったときの率直な感想をいただけますか?
和田「正直、うれしいというよりホッとしましたね。9月に監督に就任してから、ほぼずっと降格圏内にいて、最後の最後にようやく脱出することができました。残留が決まってからは、いろいろな方から電話やメールをいただきましたよ。中には、『あれっ、これ誰や?』という番号もあって、かけ直してみたら、ずっとご無沙汰していた知人から、『おー、感動したよ!』なんて。そんなやりとりを通じて、徐々に達成感が芽生えてきましたね。優勝ではなく、あくまで残留ですけれど(苦笑)」
叶屋「私も、和田監督同様です。正直、組織のトップとして、最悪の展開も覚悟していました。最終的には、事業サイドは収入の範囲内で運営を行うことができましたし、チームもまたJ1リーグで戦うことができる。満足というわけではありませんが、最低限の結果は残せたかなと」
----今季、組織やチームのトップとして、どのような信念を持って、取り組んでいたのですか?
和田「私は『一体感のあるチームづくり』を掲げてきました。『誰が出ても同じサッカーができる』『一緒に笑って、一緒に泣ける』そんなチームづくりです。

実は、シーズン途中で監督の要請を受けた際、一度はお断りしているんです。『このタイミングで引き受けるのは厳しいです』と。その後、三木谷(浩史)オーナーから電話をいただいたり、叶屋さんとお話しさせていただいたりして、最終的には、15年お世話になっているヴィッセルのために引き受けることにしました。ただ、やるからには、絶対に言い訳したり、悔いを残したりはしたくなかった。妻からは『もし残留できなくても、あなたのせいじゃないわよ』なんて言われましたが、『いや、そんなわけにはいかない』と。自分のキャリアを賭けた以上、『一体感のあるチームを作って必ず残留させるんだ』という思いで取り組みました」
----その結果が、最終節までの残り7試合、4勝3分という成績につながったのですね。では、叶屋社長はどんな信念を?
叶屋「私は経営者ですから、当然収支をみたり、組織をマネジメントしたりすることが求められます。しかし、それらはすべて『ヴィッセル神戸が勝つ』ためです。負ければ、どんなことを言われても受け入れるしかありません。実際、9戦勝利なしで迎えた名古屋グランパス戦(1-2で敗戦)の後は、居残るサポーターの前に出ていき、30分間以上彼らの厳しい声に耳を傾け続けました。ただし、それを恐れていては前には進めません。何を言われても真摯に受け止め、やる以上は、『勝利』を目指し続ける。そういう信念を持って取り組んできました」
コミュニケーションが、選手や職員の主体性をもたらす
----お二人が共通してお話しされている一体感は、日ごろのどのような取り組みを通じて生み出されているものなのですか?
和田 「選手やスタッフが何でも言い合える雰囲気づくりを意識してきました。そのためにも、できるだけ私の方から話しかけるようにしています。パフォーマンスが下がっている選手がいたら、『何か悩みでもあるんか?』と本質(サッカー)以外のところから関わってみたり、茂木(弘人選手)のような職人肌タイプには、あえてスキンシップを図ってみたりとかね。こうして普段から個々にあわせたコミュニケーションを交わしていくことで、私自身も選手の状況を把握することができますし、選手たち同士も気軽にモノが言える環境が生まれていったと思っています」

----そうした雰囲気づくりは、選手にどのような影響をもたらしたのですか?
和田 「影響をもたらしたかは分かりませんが、今季は、特に試合に出られない選手が素晴らしかった。たとえサブ組でも必死にプレーし、レギュラー陣を鼓舞し続ける。宮本(恒靖選手)なんかも、試合に出られず悔しい思いをしているはずなのに、レギュラー陣に自分のこれまでの経験をもとに惜しげもなくアドバイスをしていた。普通なら、『俺だって出たいのに…』となって当たり前の状況ですよ。それでも、『チームの勝利』というベクトルに向かって、みんなでコミュニケーションを取ってやれた、というのは、私にとって勝利と同じくらいうれしいことでした。毎試合2日前には、選手だけでランチミーティングを行うなど、主体性も高まっていきましたね」
----叶屋社長は、そんな和田監督の取り組みを、どのように見ていましたか?
叶屋 「和田さん自身は、コーチ時代とそんなに変わらないように見えました。ただ、一番の違いは『決断』でしょうね。選手起用、戦術など、すべての最終決定責任は監督にあるわけです。しかも、終盤は、もう全勝しか許されないような状況。そうした極限状態の中、経験の少ない高校生の小川(慶治朗選手)や19歳の森岡(亮太選手)を使い続けた、という決断に、『腹が据わっているな』と思いました」
和田 「自分では、そういう意識はないですね。普段からのコミュニケーションを通じて、判断材料を数多く手にしていましたから、自分にとってはいずれも納得した決断でした。『どんな結果になろうとも、この決断に悔いはない』。常にそういう気持ちで、準備し本番を迎えていました」
----一方、事業サイドは、どのような取り組みをされていたのですか?
叶屋 「クラブ全体の一体感の醸成を意識していましたね。チームサイドと事業サイドとでは、活動場所も離れていますし、当初は精神的な距離感もありました。職員は選手の名前を知っていますが、選手のほうは、一部の関わりある職員の名前しか覚えていない、なんていうことも。
そこで、できるだけ多くの職員が練習場に顔を出す仕組みを作りました。例えば、事業サイドには、『選手からサインをもらってくる』という仕事があるのですが、それを担当制ではなく、持ち回りにし、職員には名札を付けてもらい、選手に顔と名前を覚えてもらうようにしたのです。こうした取り組みが実を結んだのか、今季終盤には、職員が自発的にアイデアを出してくれるようになりました。(試合中、サポーターが一丸となって、選手に熱い声援を送れるよう、)どのチケットをお持ちの方でもゴール裏のサポーターズシートに入れる企画も、職員主導で進めてくれましたしね。
プロの世界は、モチベーションや気持ちだけで勝てるほど、甘くはありません。でも、勝利のためには、こうした結束力や一体感は絶対に不可欠。クラブ全体を巻き込んだ関係構築は、今後もヴィッセル神戸の伝統にしていきたいですね」
無意識に取っていたコミュニケーションを、意識してできるように
----弊社は9月より、こうした取り組みを、コーチングパートナーという立場からサポートさせていただいていますが、そもそも叶屋社長が、組織にコーチングを導入しようと思われたきっかけは何だったんですか?
叶屋 「以前から、マネジメントをうまくいかせるには、信頼関係の構築が重要だと思っていました。そのために、『コミュニケーションの絶対量を増やすこと』『ティーチングだけに依存しない関わりを身につけること』に興味を持つようになったのです。ただし、私一人ができるようになったところで影響力は知れています。コーチングを組織内で共有し、浸透させることで、深い信頼関係を築きたかった。そこで、コーチ・トゥエンティワンさんに協力をいただこうと思ったわけです」
----ここまで振り返ってみて、印象に残っているプログラムなどはありましたか?
 叶屋「桜井(一紀 コーチ・トゥエンティワン取締役社長)さんによるエグゼクティブ・コーチングは機能していますね。チームの勝利、一体感に向け、メンバーと関わるとき、いかに自分の意見を言わずに相手から引き出すことができるかをテーマに、コーチを受けています。並行して、電話会議のプログラムでトレーニングを重ね、現場で実践。桜井さんとの二人三脚により、いつでも意識して行動できるようになってきています」
叶屋「桜井(一紀 コーチ・トゥエンティワン取締役社長)さんによるエグゼクティブ・コーチングは機能していますね。チームの勝利、一体感に向け、メンバーと関わるとき、いかに自分の意見を言わずに相手から引き出すことができるかをテーマに、コーチを受けています。並行して、電話会議のプログラムでトレーニングを重ね、現場で実践。桜井さんとの二人三脚により、いつでも意識して行動できるようになってきています」
和田 「私は佐藤(陽子 コーチ・トゥエンティワン ディレクター)コーチと深い関係性を築かせていただいています。相手の考えの引き出し方や、事実をポジティブな視点で捉える姿勢など、指導者としても学ぶべきものは多いですね。
例えば、勝たないといけない試合で引き分けてしまったとき。勝ち点3を計算していた中、勝ち点1しか取れないのは正直痛い。しかし、その状況を分かった上で、佐藤コーチはあえてこうおっしゃるんです。『勝ち点が1増えてよかったですね!』と。それを聞いた私は、『そうやな、こうして勝ち点を積み上げていけば、必ず最後に何か起こるはずや』と言い聞かせ、次の試合に切り替えることができました」
----他に効果を感じているものはありますか?
和田 「電話会議トレーニングですね。この系統だったプログラムは、私にとって、日常のコミュニケーションを意識的に振り返る機会になっています。私は、選手個々とのコミュニケーションをある意味、無意識に行っていますが、トレーニングを通じて、『あー、やっぱりこのアプローチでよかったんや』と再確認することができています。
また、トレーニングのカリキュラムにもある『4つのタイプ分け』もデータベース作りの参考にしています。選手、コーチ陣全員にも受けてもらい、個々のタイプを把握できたことで、『思っていたとおりやな』『もっとこういう関わりをしたほうがいいな』と、より自信を持って個別対応できるようになりました」
ヴィッセルに関わるすべての人と一体感を持って戦いたい
----では、最後に、来季の抱負を聞かせてください。
 叶屋
「まず、チームとしては、今季のような残留争いではなく、一つでも高い順位を狙っていかなくてはなりませんし、クラブとしては引き続き収支均衡、独立採算を実現させたいと考えています。
叶屋
「まず、チームとしては、今季のような残留争いではなく、一つでも高い順位を狙っていかなくてはなりませんし、クラブとしては引き続き収支均衡、独立採算を実現させたいと考えています。
また、それを実現させる上でも、クラブ内にもっとコーチングやコミュニケーションの重要性を浸透させていきたいですね。そのためには、ある程度仕組みも必要。コーチ・トゥエンティワンさんのプログラムを通じて、継続的に『一体感のあるクラブ』の構築を目指していきます。それを基盤に、ファン、サポーター、スポンサーなどあらゆるステークホルダーとの関係性もさらに深めていきたいです」
和田 「コミュニケーションはクラブやチームにとって、間違いなく大事な要素。来季は、はじめから今季の終盤に見せたような一体感や、『一緒に笑い、一緒に泣ける』雰囲気を作っていきたい。それができれば、上位進出も夢ではありません。ヴィッセルに関わるすべての人と一緒に、2011年シーズンを戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします!」
----来季もコーチングパートナーとして、さらなるサポートをしてまいります。本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。
【インタビュー実施日:2010年12月15日】
聞き手:コーチ・トゥエンティワン 五十嵐 朝青
構成:コーチ・トゥエンティワン 花木 裕介
カメラ:コーチ・トゥエンティワン 勝山 紘行
《 質問 》 この記事を読んでのあなたの感想は?
- ◆ とても役に立った
- ◆ 役に立った
- ◆ 普通
- ◆ あまり役に立たなかった
- ◆ 役に立たなかった
☆ 投票結果を見る
ヴィッセル神戸でも導入している組織向けコーチングプログラムのお問合せはこちら