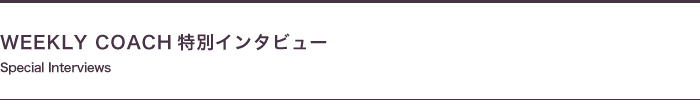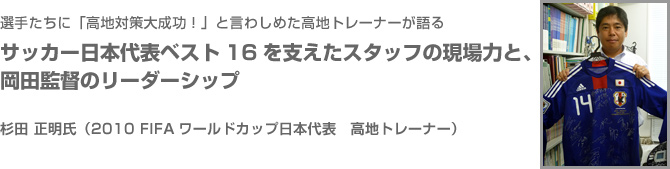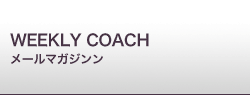7月中旬にスペイン代表の優勝で幕を閉じた2010 FIFAワールドカップ。日本代表の活躍に眠れない日々を過ごした方も多いのではないでしょうか。今回は、そんな日本代表選手のハイパフォーマンスを支えた高地トレーナー 杉田正明氏に、開幕までのスタッフや選手の取り組みや、劇的な方針転換を行い、チームを勝利に導いた岡田監督のリーダーシップについて語っていただきました。あの感動の裏側には、愚直、かつ確実な前進があったのです。

- 杉田 正明氏
2010 FIFAワールドカップ日本代表 高地トレーナー
三重大学教育学部 保健体育科 准教授三重大学大学院修了後、1991年から東京大学教養学部助手、東京大学大学院総合文化研究科助手を経て、1999年4月より三重大学教育学部准教授に。日本オリンピック委員会(JOC)情報・医・科学専門委員会委員、JOC科学サポート部会長、JOCロンドン対策プロジェクトメンバー、第29回オリンピック競技大会(中国・北京)日本選手団支援スタッフ、第15回アジア競技大会(カタール・ドーハ)日本選手団スタッフ、(財)日本陸上競技連盟・科学委員会副委員長、高所トレーニング環境システム研究会専門委員、三重大学陸上競技部監督等を務める。
当初、合宿までだった滞在予定が、急遽本大会へも帯同することに
--------まずは、サッカー日本代表、ワールドカップベスト16、おめでとうございます!
ありがとうございます! これまでもオリンピックなどに帯同したことはありましたが、ワールドカップは国内外において、取り上げ方や注目度が桁違いな大会でしたね。今も新聞や雑誌など、10本以上の取材依頼を受けていて、かなり慌しい毎日です。
--------そんな中、今日はお時間をいただき、ありがとうございます。早速ですが、杉田先生は、どのような経緯で日本代表の高地トレーナーになられたのですか?
私はもともと陸上選手で、その関係もあって、高地トレーニングの研究に取り組むようになりました。90年代はマラソンで有名なボルダーをはじめ、さまざまな高地トレーニングの場で研究を重ね、現在は三重大学で選手の育成もしながら研究を続けています。
今回は、初めに日本サッカー協会・チーフアスレティックトレーナーである早川直樹さんに1月下旬に声をかけていただき、その後、2月に岡田監督から直接、要請を受け、「高地トレーニングの専門家」として日本代表に帯同することになりました。
--------高地トレーニングは、どんな目的で行われたのでしょうか?
今回日本代表は、標高1,400m以上の会場で、グループリーグ3試合のうち2試合(カメルーン戦、デンマーク戦)を戦いました。
標高の高い場所は、空気中の酸素が少ないため、何も準備をしていないとすぐに酸欠状態になってしまう。ですから、日本代表チームは、高地の会場に行っても平地と同じように動ける状態を作るため、スイス・ザースフェー(標高1,800m)で合宿を行ったのです。私はそこで、日頃の研究を活かして、低酸素マスクや高酸素吸入装置を取り入れたり、日々選手の尿を検査したりするなどしながら、個々のコンディション作りに務めました。
-------帯同期間はどのくらいだったのですか?
ワールドカップ予選から長期的に携わってこられた5名のトレーナーおよびドクター(以下、スタッフ)の方とは違い、5月21日の代表合宿から帯同しました。最初はスイス合宿までという約束だったのですが、協会の方々に打診を受け、結果的には南アフリカまで同行することに。
短期間の関わりとはいえ、初戦のカメルーン戦前夜はさすがに眠れませんでした。「選手の足が動かなくなったら、自分の責任だ…」と思いながら、勝利を願っていました。結果的に勝利を手にしたときは、うれしさよりもホッとしたことを強く覚えています。
今回、南アフリカ帯同を快く許可してくださった三重大学と所属の教育学部、そして、私の授業の穴を埋めてくださった先生方には感謝してもしきれません。
スタッフの高い現場力が、選手に自信を与える原動力に
-------本選間近にスタッフとして入られた杉田先生の目には、日本代表のチームマネジメントはどのように映りましたか?
何といっても特徴的だったのが、本番までの周到な準備ですね。選手に余計なストレスを与えないよう、素晴らしい施設や環境が用意されていました。食事に関しても日本人シェフが2名帯同するなど、すべての準備が勝利のために行われていました。実際、サッカーの専門家ではない私を呼び、高地対策に力を入れたのも、そうした周到な準備の一環だといえるでしょうね。
--------選手が万全の状態で本番を迎えるためには、コミュニケーションにおいてもさまざまな工夫があったのではないでしょうか?
その通りです。まず、スタッフは連日ミーティングを重ね、選手個々のコンディションを完全に共有していましたし、そこで挙がった情報は、精査した上で監督やコーチに伝えていました。それによって、「あるスタッフは知っているけれど、別のスタッフは知らない」といった漏れがなくなり、心地よい一体感が生まれていました。
また、選手のコミュニケーションタイプや特徴に合わせた個別対応もなされていました。私自身、スタッフの方たちと、「この情報は、専門家である自分から伝えるべきか、それとも、付き合いの長いトレーナーに伝えてもらうべきか、または、あえて伝えないでおくべきか、どのようなニュアンスで伝えるか」といった議論を常に交わしていたような気がします。

尿検査の結果一つとっても、「必ず報告してほしいと思う選手」「何かあったときだけ伝えてほしい選手」「『どんな数値でも、自分は自分だから』と情報をあまり気にしない選手」と様々。スタッフは、こうした選手の特徴をデータベースにして、それぞれに合った対応を心がけなければなりません。
今振り返ると、スタッフの方は全員が「高い現場力」を有していました。現場力とはつまり、「場の空気を読み、その場その場でもっとも適した行動を起こせる力」。それによって、組織はうまく機能し、一つのベクトルに向かって、進み続けることができたのではないかと思います。
選手たちが「やるだけのことはやった」という自信を持って、本番である6月14日を迎えられたことは、背景にスタッフの高い現場力があったことも大きいと思います。
勝負の最前線に立ち、全責任を負う立場で、「スパッ」とダイナミックに変えることができる、岡田監督のリーダーシップ
--------先ほどのお話で、「情報は、精査した上で監督に伝える」とおっしゃっていましたが、杉田先生は岡田監督とはどのようにコミュニケーションを交わしていたのでしょうか?
岡田監督は、情報収集に対して、非常に意識の高い監督でした。とにかくあらゆる情報を手に入れて、それを元に徹底的に考えて決断を下しているようでした。そんな監督に対して、私が心がけていたのは、「短い言葉でいかに自分の伝えたい意図を盛り込むか」ということ。私の場合は経験上、一度話をすれば、相手がどのようなコミュニケーションを望んでいるのかが大体分かります。岡田監督の場合は、「前置きやくどくどした話」をあまり望まない傾向があるように感じたので、端的に自分の意図を伝えるようにしていました。
例えばこんなやりとりがありました。ある日の朝、選手の疲労度を考慮し、「今日の練習は2回よりも1回のほうがいいと思うか?」といった質問を監督から受けたのです。私の役割は、高地トレーナーとして、計測した数値を正確に伝えることでしたが、この場合、ただ数字を出すだけでは意味がありません。「コーチ的研究者」を自負する私は、その数字を現場で活用してもらうため、監督の質問に対して、「数字+明快な答え」を提示しました。「数値が●●なので、今日は1回の方がいいと思います」と。
恐らくこの場面で、「数値は●●ですから、■■の可能性があると思うので、そうなると▲▲だったとき、××になるかもしれません。それだと……」と岡田監督が求めていない理屈ばかりを伝えていたら、信頼は得られなかったと思います。
とはいえ、いくら自分の考えを提示したところで、最終的に決断するのはすべて監督です。岡田監督の決断力、判断力は間近に見ていても、本当にすごかったですよ。
--------どのようなところがすごかったのか詳しく教えていただけますか?

対戦相手や選手のコンディションなど、あらゆる情報を収集する反面、変えるべきところは「スパッ」とダイナミックに変えられるところですね。普通、こうした重要な大会の場合、前例とかがあったら、なかなか変えられないじゃないですか。でも、岡田監督は違う。戦術やメンバーもダイナミックに変えましたし、中でも、初戦を3日後に控えた1日を丸々完全休養に充てたことです。本番3日前にまったく練習をしないことは、それまでであれば考えられなかったようですよ。でも、監督は尿検査を含むあらゆる情報から選手のコンディションを的確に判断し、勝つための決断を下しました。
今思えば、この日休んでいなかったら、あの初戦はどうなっていたか…と思わなくもないですね。コンディションが勝敗を決めるすべてではないんですが、それほど大きな1日だったと私は思っています。勝負の最前線に立ち、国民の期待と全責任を一身に背負う立場で、こうした判断ができる。カメルーン戦の勝利、そして、グループリーグ突破は、岡田監督の決断力をはじめとしたリーダーシップなくしてはありえなかったでしょう。
選手の寄せ書きが入ったユニフォームは一生の宝物
-------先ほど、杉田先生は、「一度話をした人であれば、どのようなコミュニケーションを望んでいるか大体分かる」とおっしゃっていましたよね。コーチ・トゥエンティワンでは、「タイプ分け」という、自身や他者のコミュニケーションの傾向を図ることができるテストを提供しているのですが、こうしたテストをもし日本代表チームに導入していたらどうなっていたと思いますか?
(「タイプ分け」の冊子をめくりながら、)確かにこういう要素を理解することも大切ですが、ワールドカップのような短期決戦の舞台では、監督・スタッフは、コミュニケーションや決断を瞬時に行っていかなくてはなりません。選手も同様です。個々のメンバーのことが十分分かっていなければ、ピッチ上で、100%の力を発揮することはできなかったでしょう。ですから、彼らはすでにそうした力を自然に身につけていたと思います。
ただ、自然とできる人ばかりではないでしょうから、客観的に自分や他者のタイプを知っておくことは、今の世の中、必要になってくるのかもしれませんね。私もこれからは大学の准教授という役割に戻りますので、今度授業で使ってみても面白いかも…。
-------そのときは、ぜひお声かけください。では、最後に杉田先生なりに今回のワールドカップを振り返っていただけますか?
今回、私は初めての帯同で、最初はいわば「お客様」状態。しかし、最後になってようやく、チームスタッフの一員になれたなと感じた瞬間がありました。

パラグアイ戦終了後、チーム全員で食事を取ったときのこと。翌日帰国ということもあり、会場は名残惜しい空気に包まれていました。そんな中、徐々に席を立ち始めた選手のうちの一人、GKの川島永嗣選手(ベルギー・リールセ所属)がiPhoheを手に近寄ってきたんです。そして、私にひと言。「先生、一緒に写真撮ろうよ!」と。また、「連絡先教えてよ」と言ってきてくれた選手もいて、このときようやく、「自分は本当に彼らの役に立つことができたんだな」としみじみ思いました。
その後、大学の研究室に戻ってから、さらにうれしかったのが、選手たちの寄せ書きが入ったユニフォームが届いたこと。「高地対策大成功!」と書かれたこの一着は、私にとって一生の宝物です(写真参照)。
これからも今回の経験を活かして、さらに高地トレーニングの研究を通じて、さまざまなスポーツに関わっていきたいと思います。
-------今後のご活躍を楽しみにしています。今日はお忙しい中、ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました!
聞き手・カメラ:コーチ・トゥエンティワン 花木 裕介
コーチ・トゥエンティワン 永崎 智晴
今後、低酸素マスクの独自開発や、マスクを使ったトレーニングを本格的に展開していかれるという杉田先生。そんな杉田先生の活動にご興味をお持ちの方は、コーチ・トゥエンティワンまでその旨ご一報ください。
本文中でご紹介している「タイプ分け」は、これまで20万人以上のビジネスパーソンが受けている人気テストです。あなたも、ご自身のタイプを把握し、今後のコミュニケーションに活かしてみませんか?
《 質問 》 この記事を読んでのあなたの感想は?
- ◆ とても面白かった
- ◆ 面白かった
- ◆ 普通
- ◆ あまり面白くなかった
- ◆ 面白くなかった
☆ 投票結果を見る